HOME > ゴルフ場の樹木管理セミナーTOP > 平成27年度西日本地区報告
NGK・GGG共同主催 平成27年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」西日本地区 報告
平成28年3月7日(月)、豊川市にある平尾カントリークラブを会場として、一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会(NGK)および公益社団法人ゴルフ緑化促進会(GGG)の共催による「ゴルフ場の樹木管理セミナー」が開催されました。
このセミナーは、ゴルフ場の経営者、支配人、グリーンキーパーの皆様にゴルフ場の緑地機能を高めるための適切な樹木管理への理解を深めていただくことを意図したものです。
今回はマツ枯れ防除、設計者の考えるゴルフ場の樹木、新たな樹木の導入について理論を学び、マツ枯れの防除方法などを実習していただきました。
公益社団法人ゴルフ緑化促進会 理事長 大西久光 氏による開会の挨拶では、
「GGGは今年で創立40周年となる。
40年前は第1次と第2次のオイルショックの狭間にあったものの、5年間でゴルフ場数は2倍(1970年583コース、1975年1,093コース)に膨らんだ。
ゴルフ場は環境破壊とのバッシングを受け、当時の会長であった中山素平氏が、ゴルフのイメージ回復のためゴルファーから集めた寄附金で緑化活動を始めることを提唱、これまで103億円、200万本以上の植樹を進めてきた。
近年は、東日本大震災の被災地復興のため福島県でサクラ600本を植える公園づくり、岩手県県民の森での植樹に取り組んでいる。
今や開場から40年を超えるゴルフ場が多数を占め、当時植栽し大きくなった樹木を間伐する必要性が高くなり、刈草を含め植物系のバイオマスをうまく処理、活用することに今後力を入れていきたい」
と述べられました。
来賓の平尾カントリークラブ・代表取締役社長 高桑 耐 氏からは、
「当クラブは1975年の本オープンから41年目を迎える。
自然の地形を生かしたテクニカルな27ホールである。
当時植栽した樹木が大きくなり、グリーン周り、フェアウェイで日照や通風を妨げ、あるいは芝生やカート路での根上がりなどの問題が生じている。
先般、樹木を伐採した跡をみてみると、倒した形跡がない。どうしたのかと尋ねると、樹木が大き過ぎて、3方向に売店など障害となるものがあったため、倒さずにクレーン車を使って樹木を吊し切りする方法で対処したという。
なるほど、樹木のことを考えて管理することが大事と思った。
このセミナーで勉強したことを、これから5年計画で進める樹木の間伐に役立てていきたい」とご挨拶がありました。

平尾カントリークラブ 高桑代表取締役社長
座学の最初の講義は「ゴルフ場をマツ枯れから守る」について、二井一禎氏(京都大学名誉教授)から、「マツ枯れ発生の経緯」、「マツ枯れの感染環」、「健全なマツを守る」、「枯死木を取り除く」、「マツ枯れ防除の要点」について解説いただきました。
衰弱、枯死木は例外なく徹底して駆除する、防除はゴルフ場の場合、地元行政ととの調整が不可欠、であることを力説されました。
2番目の講義は「ゴルフコース設計者から見たゴルフ場の樹木管理」について、佐藤謙太郎氏(株式会社 M&K代表取締役)から、「ゴルフ場における樹木の重要性」、「ゴルフ場の樹木配置のポイント」、「樹木による戦略性と景観形成」、「適正な樹木管理」を平易に説明していただきました。
落葉樹と常緑樹、高木と中木、立木密度、花木の配置などバランスが樹木の配置において重要であり、変化と戦略性をあわせ持つ林帯ライン、グリーンへの朝日、風通しを良好にすること、落ち葉の影響を少なくする落葉樹の配置を考えることが望ましいコース設計となる。
何よりも、いかにコース委員会、理事会に樹木の剪定・間伐の効果を理解してもらい、予算を認めてもらうかが重要、と指摘されました。
3番目は、「新たな樹木の導入によるゴルフ場の管理」について、濱野周泰氏(東京農業大学造園科学科教授)から、「樹木の導入には」、「緑を造成するための要件」、「林帯づくりと植栽の要点」「既存マツ林への広葉樹の植栽」「樹木管理と樹林の育成」をわかりやすく解説していただき、育てる緑、まもる緑、抑制する緑という植える目的を明らかにすることを強調されました。
3講義通した13時20分まで長時間の座学となりました。

座学会場全景

京都大学 二井名誉教授

(株) M&K 佐藤代表取締役

東京農業大学 濱野教授

実習会場全景
クラブ食堂での遅い昼食の後、あいにくの小雨の中、クラブハウスに近い北9番ホールの実習場所へ移動し、参加者は4グループに分かれ、各々20分程度で4種類の実習メニューを同時進行で進めました。
(1)伐倒くん蒸(薬剤)
(2)樹幹注入(マツ枯れ予防)
(3)樹幹注入(広葉樹害虫予防・ナラ枯れ予防)
(4)土壌灌注(マツ枯れ予防)
クラブのご厚意で、当日実習のため北コースはクローズとなりました。

実習風景

マツノマダラカミキリ駆除の伐倒くん蒸
(協力:サンケイ化学)

広葉樹害虫駆除の樹幹注入
(協力:サンケイ化学、エムシー緑化)

ナラ枯れ予防の樹幹注入
(協力:サンケイ化学)

マツ枯れ予防の土壌灌注(協力:住化グリーン、
保土谷アグロテック、大同商事)

マツ枯れ予防の土壌灌注
(協力:石原バイオサイエンス)

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 大石専務理事
実習終了後、再び座学会場へ戻り、一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会大石専務理事より八王子カントリークラブの「緑化資源“堆肥化プラント”の取組」についてのご紹介と閉会のご挨拶をいただきました。
剪定枝、伐採木、刈草を径50㎜以下に一次破砕、最終的に4.5㎜以下まで破砕を繰り返し、戻し堆肥、攪拌、切り返し、熟成の工程を経て完成した堆肥は、土壌改良を目的にフェアウェイ等に全量散布している。
この効果は、(1)植物系廃棄物の処分費用の削減、(2)土壌改良によりサッチ(枯れて腐った葉)の発生減少、(3)農薬・化学肥料の使用量の削減、(4)目砂に使う砂を堆肥で代替、(5)とくに夏季の乾燥に耐えられ散水量の削減として現れている。
バイオマス利用の試みは、ゴルフ場の経営改善、プレイアビリティの向上、そして地域経済へ波及する可能性を持つことから、次年度以降のセミナーでは積極的に取り上げて実践に繋げていきたい、と話されました。
今回のセミナーには西日本地区から約37名(関係者を除く)の皆様のご参加をいただき、そのうちゴルフ場スタッフは約6割近くを占め、午後4時過ぎまで熱心に研修されました。
実習の実施にあたり、サンケイ化学(株)、(株)エムシー緑化、住化グリーン(株)、保土谷アグロテック(株)、大同商事(株)、、石原バイオサイエンス(株)の各社より資材提供と専門職員の派遣にご協力をいただきました。
なお、当センターは、本セミナーの企画・運営に協力致しました。
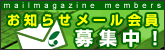

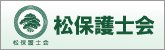
公益社団法人ゴルフ緑化促進会 大西理事長