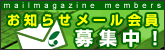HOME > 機関誌・技術図書 > グリーン・エージ > バックナンバー > 2021年2月号
2021年2月号 No.566号
特集:樹芸・工芸の力で地域の活力を高める
全国の漆消費量は2018年に37.7トン、消費量の5%程に当たる1.8トンは国内生産され、文化財建造物の保存修理に必要な国産漆は年平均で約2.2トンと推計されます。
落葉樹のウルシから採られる漆、染料に使われる草本の紅花といった特用林産物や工芸作物など、古くから営まれてきた樹芸・工芸の力で再び地域の活力を高める取組を紹介します。
表紙:椿の種子を手でひとつずつ拾う「トリッピロイ」(東京都利島)
|
 |
目次
特集:樹芸・工芸の力で地域の活力を高める
| 今日の課題:地域の植物を利用する新たな視点 | 東京大学名誉教授 谷田貝 光克 |
| 「循環」によってつくられる工芸が地域を豊かにする | 広島市立大学 芸術学部 講師 青木 伸介 |
| 椿を通して"子どもが帰ってくる島"をつくる | 東京島しょ農業協同組合 利島支店 加藤 大樹 |
| 静岡の漆文化 ―Shizuoka japan― の発信 | オクシズ「漆の里」協議会 |
| 幻の伝統品種「松山櫨」を未来へつなぐ | 松山櫨復活委員会 矢野 眞由美 |
| ものづくりを通した交流人口を定住につなぐ生活工芸村 | 三島町生活工芸館 館長 二瓶 仁志 |
| 伝統の「最上紅花」生産による地域の活性化 | 山形県紅花生産組合連合会 副会長 今野 正明 |
| サルトリイバラと歩んできた15年の道程 | (株)伊豆緑産 代表取締役社長 石森 良房 |
| 良質な漆の生産とウルシ材の利用を目指す健全なウルシ林の造成 | (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所 田端 雅進 |
連載・記事  過去の連載一覧
過去の連載一覧
トピック ベニバナの来た道 ―DNA解析から見たベニバナと「最上紅花」の起源― |
山形大学農学部 准教授 笹沼 恒男 |
人と環境<31> 縄文時代の植物利用 |
東京大学総合研究博物館 特任研究員 佐々木 由香 |
未知しるべ<11> とうがらしの世界 ―とうがらしの辛さの秘密― |
信州大学 学術研究院農学系 准教授 松島 憲一 |
昆虫たちからみた里山の再生<15> フユシャクの生態からみる「環境」 |
(株)地域環境計画 安岡 竜太 |
アホガミ様とぴかったん<23> 冬芽総選挙 |
樹木医・森林インストラクター、NPO法人 樹木生態研究会 副代表 岩谷 美苗 |
みりょく・あふれる「島」めぐり<2> 利尻島 〜山の島、緑の島〜 |
利尻・島ガイドセンター、利尻うみねこゲストハウス 代表 西島 徹 |